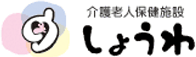先日両親と3人で温泉旅行に行ってきました。82年と78年の間、働き続けてきた両親に贅沢をさせようと企画したのですが、ホテルを予約しながら「これが最後の旅行になるかもしれない」、そんな考えが頭をよぎりました。
そして、しょうわを計画したとき32歳だったわたしも、51歳になりました。顔にはシミが目立ち、腹は出て、おしっこは勢いがなく、何よりも夜中に呼び出されると翌日の診察はふらふらな状態で、「老化」を意識せざるを得なくなってきました。「死」を他人事として診てきたわたしも、いやがうえにも「死」を自分事として考えなければならない頃になりました。
最近こんな方を診ました。
① 胃潰瘍のため3か月入院。長期臥床による廃用のため四肢は屈曲位拘縮(手足の関節が曲がった状態で固まった)。廃用(使わないことで筋力が低下、委縮)により嚥下障害となり経口摂取困難。中心静脈栄養。
② 脳出血のため1か月入院。義歯(入れ歯)が危険(飲み込んでしまう可能性がある)という理由で外され、嚥下(飲み込み)ができないと判断され経鼻栄養(鼻から胃までチューブを入れ栄養剤を流す)。管を抜かないように両手をミトンの手袋で保護しベッド柵に固定されたまま長期臥床。顎関節後退症(顎が外れてしまった状態)となり口が閉じない。また、入れ歯を外してしまったため、口腔内容積(口の中の広さ)が狭くなり、舌が前後にしか動かなくなった。このため経口摂取困難。
さて、人が「生きる」とは。人が「死ぬ」とはどう考えたらいいのでしょう。
高齢者医療、介護の先には必ず看取りというテーマがあります。高齢者に限らず、人が「生きる」先には、必ず「死」があります。
機会があるごとに「老化は進行する」「年を取るにつれ多病(病が増えていく)になる「死は必ずだれにも来る」と話しています。しかし、現在の医療、介護の現場、さらに国レベルでも、「看取り」が死を迎える直前の数日、数か月の問題としてしか議論されていないことに違和感を持ちます。尊厳死の問題も、延命するか、しないかという議論に終始して、「なぜ延命を望まないのか」という議論になっていないのではないでしょうか。「自己決定」という言葉が独り歩きしてはいないでしょうか。
「看取り」とは、その人の生き様そのものだと考えます。その人がどのようにどのように生きたか。その結果としてどのように死んだか。命の終わりを迎えるにあたって、人生を振り返った時、まだ生きていたいのか、死を受け入れるのか。ぎりぎりまで命を伸ばしたいと思うのか、それとも静かに死んでいきたいと思うのか。それはその人の生き様だと思います。それを見送る家族がどう受け入れるか、納得するか。
そして我々医療や介護を提供する者は、その人に悔いが無いように生きることを支援し、死なせることを考えなければならないと思います。
先日行われた老健全国大会で、職員が次のような発表をしました。平成26年度データ。脳卒中のため回復期リハビリ病棟で平均180日リハビリを受けた結果、経口摂取困難と判断された11人。その内9人がしょうわ入所後平均8日間で経口摂取可能となった。(柔らか食、常食)
座長は、「2人は何故経口摂取に移行できなかったのか」という質問をしてきました。そのことより、回復期リハビリ病棟で濃厚なリハビリを受けても食べられなかった人がなぜ老健で食べられるようになったのか。ということの方が問題ではないでしょうか。
命の終わりの議論を始めなければならない時が来ました。
医療の在り方、介護の在り方を根本から作り替えなければならないと考えています。死ということも含めて。